目次
~社労士監修~
【仕事と育児の両立】子供が小学生になるまでは残業制限制度を活用しよう!

子供が1歳になるまでは育児休業を取得して子育てに専念する一方、子供が保育園に入所するタイミングで仕事への復帰を考える方は多いのではないでしょうか?
仕事復帰後の当初は、まだ子供が手のかかる時期であったり、保育園の送迎もあったりしてと、時短勤務で働く方もいると思いますが、一方で子供も3歳を過ぎるころには、人見知りしなくなったり、自分で食事を食べられるようになったりして、仕事をしている間は両親に子供を預けたりと、家族のサポートを得ながら仕事への全面復帰を目指していく方も少なくありせん。
ただ子供の成長に合わせて、仕事への復帰を考えていくとき、
 「子供も少し成長したことだし、そろそろ仕事も頑張りたい!」
「子供も少し成長したことだし、そろそろ仕事も頑張りたい!」
「でも、育児もまだ大変だし、どうしよう・・・・」
と、仕事と育児のバランスが非常に悩むポイントとなります。
仕事と育児の両方を頑張ることができればそれに越したこはないですが、両方頑張りすぎて疲れて、結果として身体を壊してしまっては元も子もありません。
その時に上手く活用したいのが、「残業(時間外労働)制限制度」であり、残業時間が長くならないように残業時間に制限を設けるという制度になります。
今回は、仕事と育児を両立させたいパパ・ママを対象に、育児介護休業法に基づく「残業制限制度」について紹介していきます。
 【この記事でわかること】
【この記事でわかること】
「残業制限制度」を知ることで、
仕事と育児のバランスを上手く調整することができます!
残業制限制度(時間外労働の制限)について
「残業制限制度」(時間外労働の制限)とは、育児を理由として退職してしまう人を減らすため、仕事と育児の両立を目指せるように、育児介護休業法により制定された制度です。
妊娠や出産後の産前産後休業(産休)や、原則子供が1歳までの間に取得できる育児休業(育休)の制度は良く知られていますが、子供が1歳になって保育園に入所できることとなった場合は、同時に育児休業が終わるため、そのタイミングで仕事に復帰する方が多いのが実情です。
また復帰後当初は子供が手のかかる時期でもあり、時短勤務等の制度を利用しながら復帰される方も多いですが、子供の成長に連れて仕事への全面復帰を考えている方もいるのではないでしょうか?
ただし、仕事への全面復帰となると、仕事と育児のバランスを調整するのは難しく、「仕事も育児も頑張りたい!」と思う一方で、頑張りすぎると疲れやストレスが溜まるのも事実です。
そういった方を対象に、仕事と育児の両立を図るために設けられたのが「残業制限制度」になり、まさに仕事も育児も頑張るパパ・ママ向けの制度と言えます。
残業制限制度の対象は「子供が小学生になるまで」
残業制限制度は、小学生に就学するまで(6歳を迎える誕生日を含む年度の3月31日まで)の子供を養育している方が対象となります。
原則として、労働基準法では法定労働時間を超える時間外労働について認めていませんが、実態としては「36協定(労使協定)」によって時間外労働が認められているケースが大半であり、その場合は⽉45時間・年360時間の時間外労働が認められることになります。
今回の残業制限制度はこの36協定における時間外労働時間について、月24時間、年150時間に制限する制度になります。
【法定労働時間とは?】
労働基準法32条に以下のとおり定められています。
- 労働時間は1日8時間を超えてはならない
- 労働時間は1週間で40時間を超えてはならない
⇒36協定により、⽉45時間、年360時間の時間外労働が認められています。
⇒残業制限制度により、時間外労働については月24時間、年150時間まで制限されます。
なお、育児介護休業法では子供が小学校に就学するまでと規定しており、子供が小学生になるまでに従業員が残業制限制度の利用を申し出た場合は、企業は必ず残業制度制度を利用させなければなりません。
残業制限制度の対象にならない場合

残業制限制度は、働く従業員が会社に申請すれば利用できる制度となりますが、一部の従業員については制度の対象外となるので、自分が対象外にならないか事前に確認しておくと良いでしょう。
ケース①:雇用期間が1年未満の場合
雇用期間が1年未満の方は、残業制限制度の対象になりません。これは非正社員、派遣社員、パート・アルバイトの名称に関係なく、雇用期間で判断されます。
ケース②:所定労働日数が週2日以下の場合
所定労働日数が週2日以下の場合は、仕事と育児の両立がもともと可能であると考えられ、残業制限制度の対象にはなりません。
ケース③:日雇い労働者の場合
日雇い労働者は雇用期間という考えがないため、残業制限制度の対象にはなりません。一方でも非正社員・派遣社員、またパート・アルバイトという名称でも、他の条件を満たせば残業制限制度を利用することができます。
ケース④:事業の正常な運営を妨げる場合
あまりケースとしては少ないですが、業務に支障をきたす場合には、会社は残業制限制度の利用させないことができます。
残業制限制度と残業免除制度の違い
「残業制限制度」と似た制度で「残業免除制度」があります。
「残業免除制度」は「雇用契約に定められた所定労働時間」以外の時間=すなわち残業自体が免除される制度ですが、「残業制限制度」は残業自体は発生するものの、残業の時間数を一定制限することで、仕事と育児との両立を図ることなります。残業免除制度は残業がないので終業時刻が決まっていますが、残業制限制度の場合はその日ごとに残業があったりなかったりするため、終業時刻は日によって変わります。
★「残業なし」で仕事も育児も頑張りたい方はこちら↓
残業制限制度のメリット・デメリット
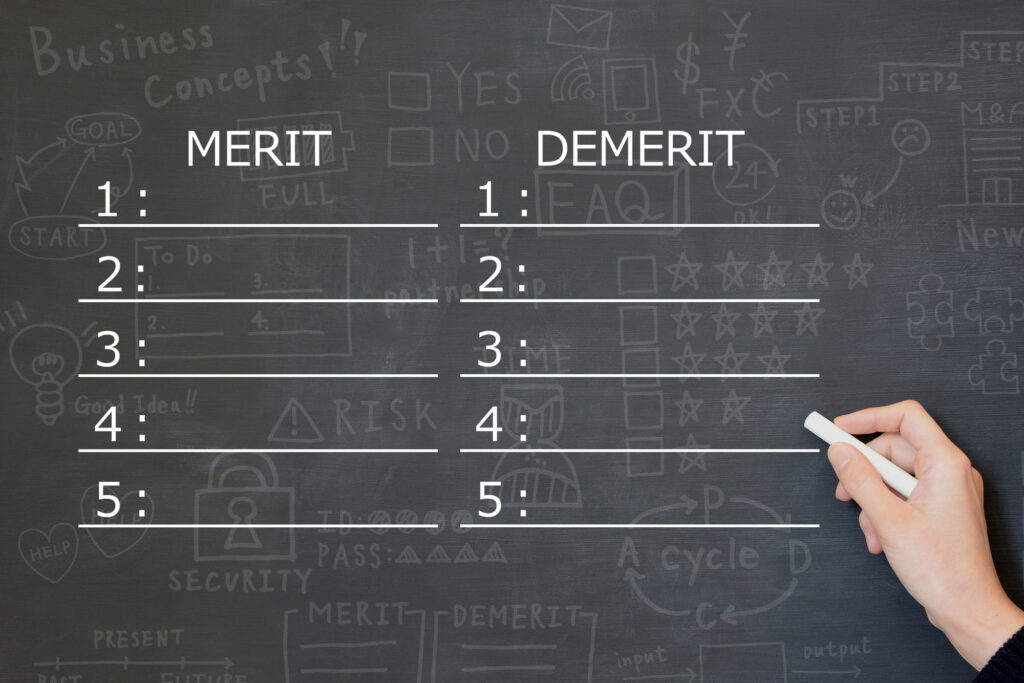
現在でも出産や育児によって退職を余儀なくされる方は少なくありませんが、残業制限制度を活用することで育児を理由に退職せず、仕事と育児を両立することが可能となります。
ここでは残業制限制度のメリット・デメリットを紹介していますので、制度の利用を検討する際にぜひ参考にしてみてください。
残業制限制度のメリット
残業制限制度を利用することで、以下のようなメリットがあります。
- 退職せずに継続してキャリアを積むことができる
- 残業代も出るため給与があまり減らない
- 育児をしながらも、仕事にも励める
やはり、残業制限制度のメリットは「育児をしながら、仕事にも励める」という点ではないでしょうか?今は男性女性に関わらず自分のキャリア形成を大事にしている方も多く、仕事も育児も両方頑張りたい方にはお勧めの制度です。
残業制限制度のデメリット
一方での利用する際に、注意しておきたいデメリットもあります。
- 1日のスケジュールが立てづらい
- 上手くバランス調整しないと、疲れてしまうこともあり
- 子供が小さいうちは利用しずらい
残業制限制度のデメリットとしては、残業があるため1日のスケジュールが立てづらい点があります。自分の裁量で上手く調整できれば良いですが、場合によっては残業と育児の大変さが重なってしまい疲れてしまう可能性があります。また子供が1~3歳と手のかかるうちは育児の負担が大きいので、「時短勤務制度」や「残業免除制度」を利用するのが良いかもしれません。
★働く時間を短くして、仕事も育児も頑張りたい方はこちら↓
残業制限の申請
残業制限制度を利用するときは、勤務先に申請する必要があります。
また急に残業制限を申請しても、会社側で人材の確保や業務量の調整等の準備が間に合わない場合があります。
残業制限を申請するときは予め上司や人事部等に相談したうえで、「いつからいつまで利用するのか?」具体的なスケジュールを話し合う必要があり、申請時期についても利用開始予定日の1~2カ月前と規定する会社は多いので、予め就業規則で確認しておくと良いでしょう。
申請による不利益な取り扱いの禁止
実際に残業制限制度を申請したい人の中には「申請したら上司から叱責されるのでは?」「利用したら嫌がらせ受けるのでは?」と心配する人も少なくありません。
なお、育児介護休業法は法律であるため、申請されれば会社はこれを拒否することはできませんし、「不利益な取り扱いの禁止」についても定められています。
例えば、残業制限申請をしたことを理由に、解雇はもちろんのこと、ハラスメント行為・嫌がらせ行為はすべて違法行為となります。
最近は育児に対する理解も社会的に広まってきましたが、もし残業制限制度を申請したことで不利益な扱いを受けたときは、最寄りの労働局に相談してみましょう。
まとめ
仕事と育児の両立というと「時短勤務制度」を利用する人が多いと思いますが、子供の成長に合わせて仕事への全面復帰を考えている方も増えており、その場合は「残業制限制度」のように仕事と育児とのバランスを上手く調整できる制度を利用しながら、徐々に復帰を目指していく方法も可能なので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
もちろん残業があることを前提としている制度なので、場合によっては家族の協力や理解は必要不可欠なのかもしれません。
制度を利用する場合、まずは子育てする夫婦で話し合うことから始めて見ましょう!
























この記事へのコメントはありません。