いざ退職を決めたとしても、退職する時の手続きというのは意外と分からないことが多く、退職後も手続きに追われたりするケースも少なくありません。
特に年金手続きについては、 将来もらえる年金に影響してくる大事な手続きである反面、あまり手続きについて知らないことも多く、


と悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回そんな悩みを解決するために、社会保険労務士である著者が退職時の年金手続き(年金の切り替え方法)について、パターン毎に詳しく解説していきます。


【この記事でわかること】

退職後の年金の加入方法がわかります!
退職後は国民年金・厚生年金保険のどちらかに加入することになります!
目次
退職後の年金の加入方法は3パターン
今の会社を退職した場合、その後の年金の加入方法は3パータンありますので、まずは自分がどのパターンに当てはまるのかを確認しましょう。
パターン①引き続き厚生年金保険へ加入する
会社員として働いている場合は、厚生年金保険に加入していることとなりますが、会社を退職した場合は一旦厚生年金保険を脱退する必要があります。
しかし、退職後に1日のブランク(離職期間)もなく、新しい会社へ再就職する場合は改めて厚生年金保険へ加入することになります。
【引き続き厚生年金保険へ加入するパターン】
・会社を退職後に1日のブランクもなく、新しい会社へ再就職した場合
パターン②厚生年金保険から国民年金(第1号被保険者)へ切り替え
会社員として働いている場合は、厚生年金保険に加入していることとなりますが、会社を退職した場合は一旦厚生年金保険を脱退する必要があります。
なお年金制度は国民皆年金のため、退職後も何かしらの年金制度に加入することになり、退職から再就職するまでにブランク(離職期間)がある場合や、退職後は独立開業して起業する場合は、第1号被保険者として国民年金に加入することになります。
【厚生年金保険から国民年金(第1号被保険者)へ切り替えるパターン】
・退職から再就職するまでにブランク(離職期間)がある場合
・退職後に起業する場合
パターン③厚生年金保険から国民年金(第3号被保険者)へ切り替え
会社員として働いている場合は、厚生年金保険に加入していることとなりますが、会社を退職した場合は一旦厚生年金保険を脱退する必要があります。
なお年金制度は国民皆年金のため、退職後も何かしらの年金制度に加入することになり、結婚して配偶者の扶養に入る場合は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。
【厚生年金保険から国民年金(第3号被保険者)へ切り替えるパターン】
・結婚による退職の場合
引き続き厚生年金保険へ加入する場合

厚生年金保険から厚生年金保険へ切り替える場合とは、退職した後に1日のブランク(離職期間)もなく、新しい会社へ再就職し、改めて厚生年金保険へ加入するパターンとなります。
退職後の厚生年金保険の脱退手続き、ならびに再就職後の厚生年金保険の加入手続きは、すべて会社経由で行うこととなり、基本は会社からの案内となるため、その案内に従って手続きを進めていくことになります。また健康保険に加入している場合はその手続きと一緒に行います。
【手続きの流れ】
・退職する会社から年金事務所へ厚生年金保険資格喪失届出が提出されます。
・会社に年金手帳が保管されている場合は、事前に返却してもらいましょう。
・再就職後、新しい会社から年金事務所へ厚生年金資格取得届出が提出され、手続き完了です。
(※新しい会社から年金手帳の提出を求められる場合があります)
なお、厚生年金保険の保険料は退職するタイミングで異なります。一言で言えば「月中に退職した場合は退職月の前月分まで」、「月末に退職した場合は退職月の当月分まで」が退職する会社の給与から控除されます。
【保険料負担について】
・資格喪失日( 退職日の翌日)の前月分までが、 退職する会社の給与から控除されます。
例①:9月30日(月末)に退職した場合(資格喪失日10月1日)
⇒9月分までが控除
※10月分は新しい会社の給与(11月分)から控除されます
例②:9月29日(月中)に退職した場合(資格喪失日9月30日)
⇒8月分までが控除
※9月分は新しい会社の給与(10月分)から控除されます

厚生年金保険の加入期間は通算されます!
厚生年金保険から国民年金(第1号被保険者)へ切り替える場合

厚生年金保険から国民年金(第1号被保険者)へ切り替える場合とは、退職後に再就職までブランク(離職期間)ある場合や、退職後は個人事業主やフリーランスとして起業する場合となります。
この場合、退職後は第1号被保険者として国民年金へ加入することとなりますが、手続きは自分で行う必要があります。
【手続きの流れ】
・退職する会社から年金事務所へ厚生年金保険資格喪失届出が提出されます。
・会社に年金手帳が保管されている場合は、事前に返却してもらいましょう。
・自分で各市町村窓口で国民年金の加入手続きを行います。
また、手続きについては14日以内に行う必要があり、また会社員時代に配偶者が健康保険の被扶養者(国民年金第3号被保険者)だった場合は、配偶者も国民年金第1号被保険者への切り替えが必要になります。(※国民年金保険料は2人分納付することとなります)

また配偶者の手続きも忘れないようにしましょう!
なお、保険料の負担については、先述したとおり退職するタイミングで異なりますので、2重で負担しないよう気をつけましょう。(2重負担となった場合でも払いすぎた保険料は返還となります)
【保険料負担について】
・厚生年金保険料は資格喪失日(退職日の翌日)の前月分までが退職する会社の給与から控除され、国民年金保険料は退職月の分から納付することとなります。
(※国民年金保険料の支払期日は翌月末日まで)
例①9月30日に退職した場合(資格喪失日10月1日)
⇒厚生年金保険料は9月分まで負担し、10月以降は国民年金保険料を負担します。
例②9月29日に退職した場合(資格喪失日9月30日)
⇒厚生年金保険料は8月分まで負担し、9月以降は国民年金保険料を負担します。

また厚生年金保険から国民年金への切り替えのタイミングについては保険料負担と同様に、厚生年金保険と国民年金のそ退職するタイミングで異なります。
【切り替えのタイミング】
・厚生年金保険の加入期間は資格喪失日(退職日の翌日)の前月までとなり、その後は国民年金保険の加入期間となります。
例①9月30日に退職した場合(資格喪失日10月1日)
⇒厚生年金保険の加入期間は9月まで(10月からは国民年金の加入期間)
例②9月29日に退職した場合(資格喪失日9月30日)
⇒厚生年金保険の加入期間は8月まで(9月からは国民年金の加入期間)
厚生年金保険から国民年金(第3号被保険者)へ切り替える場合

厚生年金保険から国民年金(第3号被保険者)へ切り替える場合とは、配偶者が同様に厚生年金保険へ加入しており、退職後はその配偶者に扶養されるパターンとなり、わかりやすく言えば、結婚や育児で会社を退職する場合がこのケースに該当します。
【手続きの流れ】
・退職する会社から年金事務所へ厚生年金保険資格喪失届出が提出されます。
・配偶者(または親族)の会社経由で国民年金第3号被保険者関係届を提出します。
※健康保険の被扶養者(異動)届出も同時に行います
なお、配偶者の扶養に入るためには年収条件と同居条件が必要となるため、条件を満たさない場合は国民年金第1号被保険者として保険料を納付する義務が発生しますので、予め年収条件や同居条件について確認しておくと良いでしょう。
逆に言えば、配偶者の扶養となることから、第3号被保険者として国民年金に加入する場合は、保険料の負担はありません。

保険料負担はありません!
【保険料負担について】
・資格喪失日( 退職日の翌日)の前月分までが、 退職する会社の給与から控除されますがそれ以降の保険料負担は発生しません。
例①9月30日に退職した場合(資格喪失日10月1日)
⇒9月分までが控除(10月分からは保険料負担なし)
例②9月29日に退職した場合(資格喪失日9月30日)
⇒8月分までが控除(9月分からは保険料負担なし)
また厚生年金保険から国民年金への切り替えのタイミングについては保険料負担同様に、厚生年金保険と国民年金のそ退職するタイミングで異なります。
【加入期間について】
・厚生年金保険の加入期間は資格喪失日(退職日の翌日)の前月までとなり、その後は国民年金保険の加入期間となります。
例①9月30日に退職した場合(資格喪失日10月1日)
⇒厚生年金保険の加入期間は9月まで(10月からは国民年金の加入期間)
例②9月29日に退職した場合(資格喪失日9月30日)
⇒厚生年金保険の加入期間は8月まで(9月からは国民年金の加入期間)
起業する場合は「社保サポ」も検討へ
退職後の加入手続きについては、保険料の負担で考えると配偶者の被扶養者として国民年金(第3号被保険者)に加入するのが一番良い方法です。
しかし配偶者の扶養となれなかった場合や、自分で起業する場合、また再就職までブランクがある場合は、一旦国民年金(第1号被保険者)への加入手続きが必要となりますので、忘れないよう注意しましょう。
なお夫婦世帯で、例えば夫が今まで厚生年金保険へ加入しており、扶養されている妻が第3号被保険者として国民年金に加入しているケースにおいて、夫が退職後に第1号被保険者として国民年金に加入した場合は、妻も第1号被保険者として国民年金に加入することになり、その分妻にも保険料負担が発生しますので、もし社会保険料を見直したい方は「社保サポ」への加入も検討してみるもの良いでしょう。
★個人事業主として起業する場合は「社保サポ」への加入も検討しよう!
社保サポ
★その他退職手続きについてはこちら↓

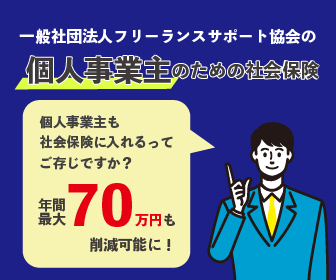



























この記事へのコメントはありません。