働き方改革によって、働き方の多様化が進んだことから、今では専業主婦家庭よりも夫婦共働き世帯が大分増え、厚生労働省「令和2年版厚生労働白書」によれば、現在は夫婦共働き世帯の割合は65%を超えており、実際に夫婦で夫婦共働きで家事・育児の分担している人も多いのではないでしょうか?
また、女性の場合は結婚や出産を機に働き方を見つめ直す機会も多く、家事や育児をしながら働く際に、「自分の裁量で自由に仕事ができること」から、特に30代の女性は個人事業主やフリーランスとして起業する方が多いと言われています。
一方で女性の場合は、結婚後に夫の扶養に入っているケースも珍しくなく、いざ起業するとなると、


と悩まれる方も多いのではないでしょうか?
今回はそんな悩みを解消します。
この記事では所得税における扶養家族の年収条件について、特に扶養に入りながら個人事業主として働きたい方向けに解説していますので、ぜひ参考ください!
【この記事でわかること】
個人事業主として働きながら、夫の扶養に入る際の年収条件がわかります!
「所得金額」がポイントとなります!

目次
扶養家族の条件とは?(所得税)
夫婦共働きの場合、夫婦ともに気になるのが、所得税法上「妻(または夫)は扶養家族になるのか?」という点です。
例えば、会社員である夫が妻を扶養している場合、夫の所得税については「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が適用され、所得税が軽減できることになりますが、妻が収入を得ることで扶養から外れるとなると、夫の所得税負担が増えることになります。
特に妻の収入が増えたことで扶養から外れ、夫の所得税負担が増えてしまうと、場合によっては夫婦合算での手取り収入が減ってしまう可能性もあるため、ここでは扶養家族となる条件=年収条件について解説していきます。(わかりやすくするため、夫=会社員、妻=主婦の家庭を想定して解説していきます)
扶養家族となるための年収条件

妻が所得税法上の扶養に入るというのは、言い換えれば、会社員である夫の所得税について「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用を受ける=所得税が軽減できることを意味します。
この「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、妻を扶養している分、夫の所得税負担を減らすことを目的としているので、逆に扶養しているとは見なされない場合は控除の適用を受けることはできません。
そのため控除の適用有無については、扶養されている妻に対して以下のとおり年収条件が定められています。
《配偶者控除の年収条件》
・年間の合計所得金額は基礎控除48万円以下であること
・給与収入のみを得ている場合は103万円以下(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)であること
《配偶者特別控除の年収条件》
・年間の合計所得金額が48万円超~133万円以下であること
・給与収入のみを得ている場合は103万円超~201万円以下であること
なお、扶養されている妻が、会社員やパートアルバイト(給与所得者)として働く場合と、起業して個人事業主として働く場合とでは、年収に対する考え方が異なるので、次にその違いについて解説していきます。
給与所得者として働く場合

会社員またはパートアルバイト(給与所得者)として働く場合は、会社に雇用されたうえで、会社から給与が支払われることになります。
配偶者控除が適用される=扶養に入るための年収条件は、年間の合計所得金額が48万円以下となりますが、給与所得者の所得金額というのは、
所得金額 = 給与 ー 給与所得控除55万円
で計算されます。
給与所得控除というのは、会社員やパートアルバイトとして働く場合の経費相当分に当たるもので、給与収入がある場合は誰でも控除が適用されるものとなります。
つまり、給与が103万円以上を超えないと、所得金額も48万円を超えないことになるため、給与所得者として働く場合は、「会社から支払われる給与が103万円を超えるか超えないか」=「扶養に入れるか入れないか」となります。
個人事業主として働く場合

一方で個人事業主として働く場合は、会社から給与が支払われるわけではないため、年収に対する考え方が給与所得者とは異なり、個人事業主(事業所得)の場合の1年間の合計所得金額は、
所得金額=収入ー経費ー青色申告特別控除(青色申告の場合のみ)
で計算されます。
つまり個人事業主の場合は、収入(売上)から経費を引いた分の利益が所得金額となります。
例えば、収入が150万円、経費が120万円なら、所得金額は差し引き30万円となり、この場合は所得金額が48万円以下となり夫の扶養に入ること(配偶者控除の適用を受けること)ができます。逆に収入が150万円で経費が100万円であれば所得金額は差し引き50万円となり、48万円を超えるため夫の扶養に入ること(配偶者控除の適用を受けること)はできません。
つまり、夫の扶養に入るには「収入を減らす」もしくは「経費を増やす」ことで自分で調整できることもできることになり、この点が給与所得者と大きく異なる点となります。
また個人事業主で青色申告をした場合、さらに10万円または65万円が青色申告控除で差し引くことができるため、収入から経費以外に何が控除できるのかを知っておくことも大切です。

配偶者控除・配偶者特別控除について
妻が個人事業主として働くとなった場合、所得金額が一定の金額以下であれば、夫の扶養に入ることができるというのは先述したとおりですが、扶養に入っている場合でも、夫の所得税が軽減される方法は2つに分かれており、1つが配偶者控除、もう1つは配偶者特別控除となります。
ここではこの2つの違いについて解説していきます。
配偶者控除

配偶者控除とは、妻の所得金額が48万円以下であれば、夫に適用される所得控除となります。
なお、妻の所得金額が48万円以下であれば、その金額に多寡に関わらず、夫に適用される所得控除額は変わりません。一方で夫自身の所得金額が一定金額を超える場合は所得控除額も低くなるのが特徴です。
| 給与所得者(夫)の 合計所得金額 |
控除額 | |
| 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上の配偶者) | |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超~950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超~1000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1000万円超 | 0万円 | 0万円 |
例えば、夫の所得金額が900万円以下(給与収入のみの場合は年収1095万以下)の場合、妻の所得金額が48万円以下であればその金額の多寡に関わらず、夫に適用される所得控除額は38万円となります。
配偶者特別控除

配偶者控除は夫の所得金額で控除額が決まっていましたが、配偶者特別控除については妻の合計所得金額によっても段階的に控除額が変わってくる点が大きな違いとなり、妻の所得金額が95万円を超えるとその金額の多寡によって、夫の所得控除額も徐々に目減りしていき、最終的には妻の所得金額が133万円を超えると夫の所得控除額はゼロとなり、扶養から完全に外れることになります。
| 配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | ||
| 900万円以下 | 950万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
| 45万円超~95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超~100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超~105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超~110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超~115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超~120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超~125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超~130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超~133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
★配偶者控除・配偶者特別控除について詳しく知りたい場合はこちら↓
扶養に入りながら働くには副業サイトへ登録しよう
今回この記事を参考にしている方は、夫(または妻)の扶養に入りながら、家事・育児もこなしつつ、自分なりの働きがいを見つけたい方が多いのではないでしょうか?
一方で家事や育児をしながら働くというのは、性別に関わらず男性でも女性でもかなりハードワークとなるため、できれば自分の裁量で自由に働くことができる、また隙間時間を見つけて気軽にできることが、働きがいにも繋がっていきます。
そのため個人事業主やフリーランスとして働く方は増えており、もちろん扶養に入りながら働いている方もいれば、会社員をしながら副業として働いている方も多くいます。
今では副業サイトもかなり増えて来ており、自分がやりたい仕事が手軽に見つかる場所、また自分がやりたい仕事を提供できる場所も増えてきていますので、もし扶養に入りながら働く際は、ぜひ副業サイトへの登録をお勧めします。
今から自分なりの働きがいを見つけてはみませんか?
★当サイトでは初心者向けの副業サイト3選を紹介しています







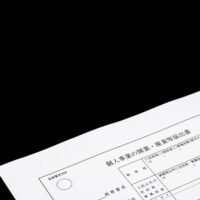


















この記事へのコメントはありません。