目次
【新しい働き方】労働者協同組合法をわかりやすく解説!2022年10月施行

厚生労働省は2022年(令和4年)10月より、労働者協同組合法が施行されることとなりました。
労働者協同組合法とは、働く人が自らが出資して組合の運営に携わることができ、協同組合の一員として働くという「新しい働き方」を実現する法律です。
これまで働くとなると会社に就職するか、NPO法人や企業組合に所属しながら活動するというのが一般的ででしたが、会社で働くとなると時間や場所の制約があったり、またNPO法人や企業組合となると設立までに時間がかかったり、認可申請までに時間がかかったりとハードルが高いのが現状です。
しかし、労働者協同組合法は、これらの課題を克服することにより、人口減少問題を抱える地方創生に役立つとも言われています。
また、労働者自らが出資するという点において、労働者が主体的に組織運営に携われることからも、労働者の働き方が一つ増えたとも言えますが、
 「労働者協同組合法によって、何が変わるの?」
「労働者協同組合法によって、何が変わるの?」
と、まだ判然としない方も多いのではないでしょうか?
今回の記事では労働者協同組合法とはどのような法律であるか、また働く人にとってどのような影響があるかを解説します。
【この記事でわかること】
 「労働者協同組合によって、個人が主体的に働くことができます!」
「労働者協同組合によって、個人が主体的に働くことができます!」
労働者協同組合法について
労働者協同組合法とは、働く個人が自ら出資することで組織運営に携わることができる「協同労働」に関する組織の設立、またはその管理、その他必要事項を定めた法律となります。
従来の働き方からすれば、組織に入って働くとなると、通常は会社と雇用関係を結び、「使用者」と「労働者」という関係で働くことになります。
一方で、労働者協同組合とは働く個人が「組合員」として出資・経営・労働という3つの役割を担うことで、組織の指揮命令下で働くだけでなく、組織運営にも携わることができ、働くことへのやりがいが期待されているとも言われており、まさに新しい働き方とも言えます。
また、この法律では協同組合と組合員との間で労働契約の締結が義務付けられており、労働者としての立場も保護もされることになります。
※参考資料
労働者協同組合 |厚生労働省
労働者協同組合の法制化を – JAPAN WORKERS’ CO-OPERATIVE UNION
労働者協同組合法が作られた背景
人口減少が著しい地方においては、超高齢化社会に伴い介護・障害福祉など幅広い分野で多様なニーズが生じています。
介護や福祉などの事業を行っている組織は主に非営利組織であり、その多くは法人格を持たず任意団体として事業を行なってきました。NPO法人や企業組合などの認可を得て事業を行っている組織が大半です。
しかし、認可が下りずに法人格を得られなかったりと、NPO法人の設立・維持の手続きが煩雑であることとなど多くの問題が存在していました。
そういった問題を解消するために、法律により「労働者協同組合」として法人格が与えられ、かつNPO法人などよりも簡単な手続きで設立できるようになります。
例えば訪問介護や学童保育、町づくりなど、地域の需要と合致した事業が誕生し、多様な雇用機会につながり、担い手が増えることが期待できるでしょう。
労働者協同組合法が作られた目的
目的条文
労働者協同組合法では以下のように目的条文が規定されています。
【目的条文】
第一条
この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。
第三条
組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。
一 組合員が出資すること。
二 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
三 組合員が組合の行う事業に従事すること。
【引用資料】労働者協同組合法
この法律では、「組合員が出資すること」「組合員の意見を反映して事業が行われること」「組合員自ら事業に従事すること」と定義しており、組合員すなわち働く個人が主体的に組織に携わることで、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、地域における課題に応じた事業が行われることを促進するものとなります。
労働者協同組合法への期待
労働者協同組合法の目的についても、少子高齢化に伴う地域における諸問題を、働く個人自らが主体的に取り組めるような組織づくりを目的としており、労働者協同組合が増えることで
- 多様な就労機会の創出
- 地域の需要に応じた事業の実施
- 持続可能で活力ある地域社会の実現
が期待されています。
労働者協同組合法の特徴
労働者協同組合法では、組合員は「出資」「経営」「労働」の役割を担っており、会社でいう株主・経営者・労働者の1人3役を担うことになります。
第三条 組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。
一 組合員が出資すること。
二 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
三 組合員が組合の行う事業に従事すること。
【引用】労働者協同組合法
一般的な働き方では、会社が労働者を雇用し、使用者の指揮命令のもとで労働者が働くかたちとなっており、出資・経営・労働が分離しています。
一方で、労働者協同組合では、働く人自らが出資・労働・運営に関わります。
労働者協同組合では仕事を通じて収入だけでなく、やりがいや労働への満足感を得ることが期待できます。
労働者協同組合法のメリット・デメリット
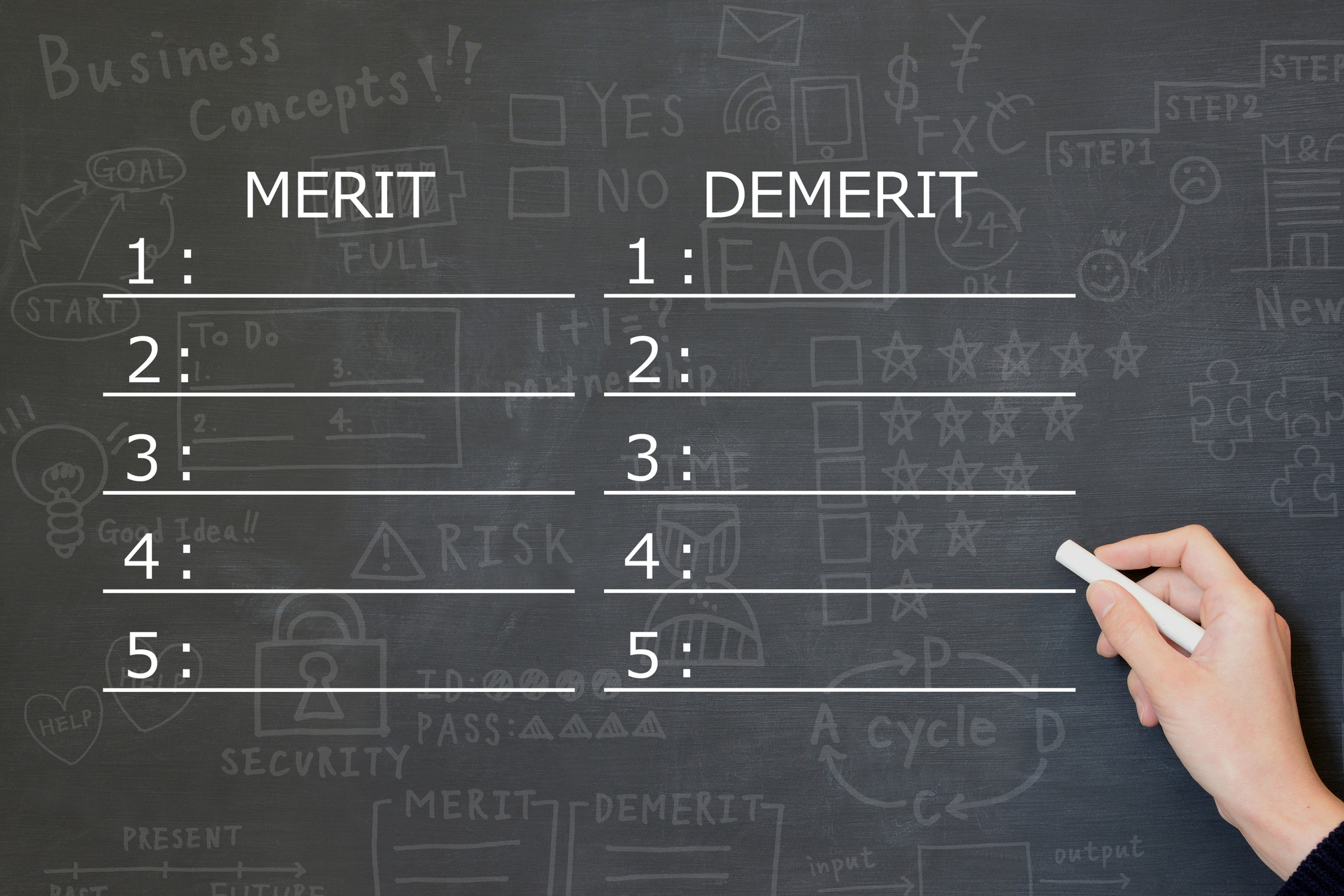
実際に労働者協同組合が作られた場合、働く人にとってのメリット・デメリットをいくつか紹介しますので、組合員として働きたい方や、仲間の組合を作りたい方は確認してみてください。
メリット
労働者協同組合法には以下のようなメリットがあります。
- 働き方の選択肢が増える
- 組合は簡単に作れる
- 地方自治体との連携可能
今までは、会社で働くか、起業するかの2者択一でしたが、今後は仲間と組合を作ったうえで自分たちで主体的に事業を行いながら働くという第三の選択肢が生まれることになります。
また組合自体は発起人が3人以上いれば、組合が設立できるので非常に手続きが簡単ですし、企業組合やNPO団体のように行政官庁の認可や認証は不要なので、設立へのハードルは非常に低いです。
【発起人】
第二十二条
組合を設立するには、その組合員になろうとする三人以上の者が発起人となることを要する。
【引用】労働者協同組合法
また労働者協同組合は「非営利団体」の扱いとなるので、地方自治体と連携を取りやすくもあり、業務委託の入札時に他の団体より不利になることもありません。もし自分たちの手で地域貢献を目指したい方は地方自治体と協力しながら事業を進めて行くことも可能です。
デメリット
逆に労働者協同組合法のデメリットについて、いくつか紹介します。
- 労働者としての保護が適切に受けられないかもしれない
- 労働条件の悪化が懸念される
労働者協同組合法では、原則として組合は組合員との間で労働契約を締結しなければならないと定められていますが、以下のとおり「組合の業務を執行する組合員」はこの対象ではなく、労働契約の締結が義務付けられていません。
【労働契約の締結】
第二十条
組合は、その行う事業に従事する組合員(次に掲げる組合員を除く。)との間で、労働契約を締結しなければならない。
一 組合の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員
二 監事である組合員
2 第十四条又は第十五条第一項(第二号を除く。)の規定による組合員の脱退は、当該組合員と組合との間の労働契約を終了させるものと解してはならない。
【引用】労働者協同組合法
また、仮に労働問題が発生した場合、組合の業務を執行する組合員については、労働法制上の「労働者」と認められるか判然としない点があり、労働者と同様に働いていたとしても、労働者保護に値しないとのことで十分な保護を受けられない可能性があります。
また労働者協同組合法では、組合員による出資、運営、労働の一体的な構造を想定しており、また構成メンバー間の近親性も影響することから、労働条件が曖昧になったり、また賃金や労働条件が不当となるか可能性も懸念されます。
【参考資料】協同労働 働き手の利益を第一に|朝日新聞デジタル
最後に
以上、労働者協同組合法について簡単に紹介して参りましたが、働き方という観点で言えば、会社員または個人事業主として働くという2者択一から、協同組合というチーム組織で働くという第3の選択肢が増えたかたちとなります。
また少子高齢化が顕著に進む中、各地域における課題は多く、地域住民による主体的な取り組みも必要ですし、価値観の多様化が進む中で多様な就労機会も必要となります。
もしからしたら労働者協同組合法の施行によって、自分自身の働き方が変わるかもしれません。







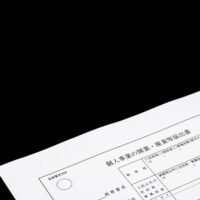















この記事へのコメントはありません。